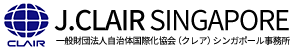昨年12月に日本でIR推進法が成立し、政府のIR実施法案の策定やギャンブル依存症対策への取り組みがはじまる中、1月17日(火)、熊本県議会議員視察団がシンガポールのIR施設について、政府の政策やルール作り、またギャンブル依存症などに対する対策方法などを調査するため、カジノ規制庁(CRA: Casino Regulatory Authority)及び国家賭博問題対策協議会(NCPG: National Council on Problem Gambling)を訪問しました。
カジノ規制庁及び国家賭博問題対策協議会について
カジノ規制庁は、内務省下の法定機関として2008年に創設された機関です。カジノ規制庁はカジノの健全かつ安全な施行を確保し、社会や人々をカジノ犯罪やカジノに起因する有害な影響から守ることを目的に掲げており、2006年に施行されたカジノ管理法(Casino Control Act)に基づき、民間事業者に対するライセンスの交付とその手順・規制の制定と監視を行っています。
国家賭博問題対策協議会は社会開発省及び青年・スポーツ省(現 社会家族開発省)下の法定機関として 2005 年に設置され、精神科医、心理学者、福祉士、カウンセラー、宗教、リハビリ等の専門家 17 名で構成されるメンバーにより、カジノだけではなく、競馬、スポーツくじなどギャンブルに起因する問題に対応することを目的として活動しています。同協議会の主な役割としては、①社会家族開発省に対するギャンブルに関する社会的懸案についてのアドバイス、②ギャンブルに関する公的教育、利害関係者との相談、ギャンブル事業者による法的責任の行使、ギャンブルが引き起こす問題の調査研究、ギャンブルに起因する問題からの本人及び家族の保護、③カジノ管理法に基づくカジノ排除プログラムの実施、④依存症治療機関への支援が挙げられます。
シンガポールにおけるカジノプレイヤーの傾向とは?
シンガポールにおけるカジノプレイヤーは、税制上、カジノに10万シンガポールドル以上預け、カジノに口座をもつプレミアムプレイヤーとその他のプレイヤーの、二つに大別されます。プレミアムプレイヤーに係る収支には5%、その他のプレイヤーに係るものには15%の税金がかかります。このプレミアムプレイヤーとその他のプレイヤーがカジノに費やす金額の合計の割合について、以前は50:50くらいだったようですが、最近はその他のプレイヤーによる金額が大きくなってきているとのことです。
カジノを訪れる民族別の割合については、圧倒的に中華系が多いとのことで、それゆえにギャンブル依存症にかかる者も中華系が多く、また若いころから高い掛け金でギャンブルを行ってきた者がギャンブル依存症などにかかりやすいとの結果が、カジノ規制庁の調査により分かっています。
カジノに関する規制のあれこれ
シンガポールにおける未成年(21歳未満)は、カジノに入場することさえ出来ず、また成人でもシンガポール人(永住者を含む)には、入場料が課されます(外国人は入場無料)。これら以外にもシンガポールでは、3つの入場禁止・制限方法を定めており、1つ目は、ギャンブル依存症などギャンブルにはまらないようにカジノへの入場禁止もしくは入場回数制限を自ら申請するもの、2つ目は家族が入場禁止・制限を申請するもの、3つ目は自己破産者や生活保護受給者などに対して法律で自動的にカジノ入場を禁止、制限するものです。
また、カジノ内の規制として、銀行ATMのカジノ施設内の設置禁止や、自己申告により1日あたりの損失限度額を設定し、損失額がその設定額を超えるとゲームを続けられないなどがあります。
今回訪問した両機関からは、カジノを導入したことによるメリットとして、観光収入の増加や雇用数の増加などだけでなく、ギャンブル依存症に対して、政府としてしっかりと体制をとるようになったことが挙げられました。特に中華系の間では、カジノができる以前から、競馬や麻雀などによるギャンブル依存症患者も存在していました。しかし、その数は限定的であったため、政府としてはあまり表立てずに対応してきました。そのため、カジノ導入は、政府がギャンブル依存症対策に注目するようになった良い契機となったと考えているとのことです。
このように、カジノの負の側面に対する対策等だけでなく、カジノを導入したことによるメリットなどについて、熊本県議会議員視察団と両機関において活発な意見交換が行われました。